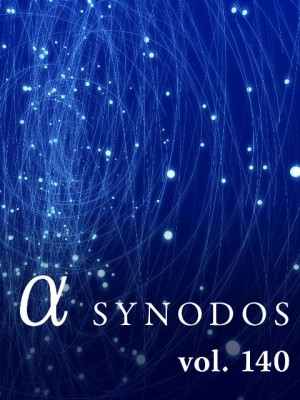2014.01.15

もうひとつの沖縄戦後史──「オッパイ殺人事件」と経済成長
電子マガジン「α-synodos」新連載! 貧困、スラム、売春、犯罪……。1960年前後の「沖縄タイムス」の記事から、戦後沖縄の知られざる側面を鋭く切り取る。
* * *
沖縄戦が終わってから13年、復帰まであと14年。1958年は、「戦後沖縄」のちょうど折り返しの時期だった。
那覇のすぐ隣にあり、いまでは閑静なベッドタウンとなっている浦添市。1958年、この街で凄惨な事件が起こった。
ある日、浦添市沢岻付近の幹線道路で、走行中のトラックに飛び込んだAという29歳の青年がいた。Aは一命を取りとめたが、「可愛いやつを殺した、俺もこの車で轢き殺してくれ」とわめいていたという。
そのすこし前。Aは、近所に住む遠縁の自宅を訪れ、同じことを話していた。「一番可愛いやつを殺した。君や親戚を皆殺しにして、俺も死ぬ」そう叫んでいた。そして、Aは、ズボンのポケットから、切り取ったばかりの血まみれの片方の乳房を取り出して、その親戚の青年に差し出したという。
前の晩おそく、Aは、同居する妻B子(19)を近所の林のなかで撲殺し、その死体とともに夜を明かした。死体の皮膚には「スキ」という文字が刃物で刻まれていた。彼はナイフでB子の死体から片方の乳房をえぐり取り、それをポケットに入れてふらふらとさまよい、死のうと思ってトラックに飛込んだのである。殺されたとき、B子は妊娠していた。
この事件は、猟奇的で残酷な殺人事件として当時の新聞などで詳しく報道されているが、青年AやB子の詳しい生い立ちまでは記録されていない。わかっているのは次のことだけである。
Aは地元の地主の長男で、8000坪の土地を相続によって所有していたが、事件当時までにはほとんど売り払っていた。定職に就かず、強盗、窃盗、傷害、暴行、放火などを繰り返し、前科7犯であった。そして、新聞記事によれば「宜野湾村真栄原新町の飲み屋で働いていたB子さんと知り合い、1万5千円の前借を支払って身うけ一緒になった」[沖縄タイムス 1958.10.21] 。B子の両親は当時、ブラジルに移民していた。ふたりはこのようにして出会い、隣町の貸家を借りて所帯を持った。ところが、Aは、犯罪を繰り返していただけではなく、独特のパーソナリティの持ち主だったようだ。それは異常な独占欲である。Aは所持金が尽きたことからB子と心中しようとしたと供述しているが、沖縄タイムスは次のように報道している。(以下、引用文はすべて原文のまま)
調べによるとAはB子さん(19)を異常なほどに愛しており、買物、入浴、どこへでもついていくといった溺愛ぶり。ときどき冗談でB子と別れるぐらいなら死んだ方がいいともらしていたようだ。一方B子さんには、心中といった暗いところはどこにもみえず事件当夜(20日よる)ふだんの通り翌日の朝めし準備もすまし、ふだん着のままスリッパをつっかけて家をでている。……Aは、B子さんがそばを離れるのを極端にきらい、隣にいっても5分とまたずによびにいったようである。B子さんに見放されるのが怖くさいきんは生活に自信を失ったことからB子さんが逃げだしはしないかという恐怖からこの犯行となったのではないかと警察ではみている。[沖縄タイムス 1958.10.21]
……B子さんは器量もよし性格も朗らかだった。AはB子さんといっしょになってからは酒もピタっと止めゴロ仲間も遠ざけ、B子さんと愛することで毎日を楽しく送っていた。買物、入浴、どこへでもいっしょについて行くというおしどり夫婦だった。しかし彼の溺愛も前科者であり、定職もなく、おまけに風貌は上らないときているため、何時も逃げられはせんかという不安がともなっていた。……B子さんがちょっと隣家に行っても5分とまたず呼びに来た。その都度“何もしなくていいから俺の側にいてくれ”と頼み込んだ。……職もなく寝たり食ったりの生活。その間、Aの土地を売って得た金も使い果たし、20ドルの借金さえつくってしまった。払う見通しも、ないので近くの小間物店からの延売も気まずくB子さんはとうとう買い物にも行かなくなった。そのためAが代りに行くことはしばしばだった。劣等意識の人一倍強いAにとってはこうしたことでB子が自分と別れるのではないかとそのことだけで頭がいっぱいになったようだ。[沖縄タイムス 1958.10.22]
昔の新聞の「あけすけな」書き方にも驚くが、ここでこの記事を引用したのは、この事件のなかに、戦後の沖縄の「ある側面」を読み取ることができるからである。
沖縄という場所は、日本にとって、さまざまな意味で「特別の場所」だ。
たとえば私たち日本人は、わずかな補助金と引き換えに多くの基地やそれにともなう問題を、あの小さな島に押し付けている。私たちは、沖縄の人びとが本土からもたらされる「莫大な」カネに依存していて、だから沖縄は、日本には楯突けない、けっきょくは言うことを聞くしかないのだと思い込んでいる。
しかし、実は沖縄に依存しているのは私たちのほうであり、沖縄の人びとがこの百年というあいだ押し付けられてきた苦難と比べれば、その引き換えに受け取るカネはあまりにも少ない、というのが真実である。私たちは、遠く離れた南西諸島の小さな島々に、国家として負担すべき多くのものを、あまりにも少ない金額で押し付けているのである。その意味で、私たちは、沖縄に依存している。
また、同時に、私たちひとりひとりにとって沖縄が特別な場所であるのは、それが、私がそれを通じて「自己肯定感」を回復できる場所だからである。
もっともわかりやすい言い方をすれば、青い海や白いビーチ、数多くの楽しい観光地によって、私たちは沖縄の長い夏を楽しむことができる。誰もがビーチで水着になり、5月から10月のあいだ、寒い日本ではなかなか楽しむことのできない夏を、私たちは享受できる。
それだけではない。沖縄は、この抑圧的で同化主義的な国家のなかで、ほとんど唯一「独自性」を残す場所である。この社会で居場所のない、生きづらい人びとの多くにとって沖縄は、「ここではないどこか」へ開く扉なのである。
沖縄に片思いをするのは、ビーチで楽しげに遊ぶ若い男女だけではない。内省的で個人主義的な多くの人びとが、自らが生まれた場所で望んで得られなかった居場所を、沖縄に見いだすのである。日本のなかで特殊な場所である沖縄に、身の置きどころのない自分を重ね合わせて、私たちは沖縄に恋いこがれる。そうした人びとは、北谷や恩納ビーチや美ら海水族館よりもむしろ、桜坂や栄町市場、あるいは竹富島や久高島などの離島に好んで行くだろう。日本のなかの独自性である沖縄のなかでも、さらにもっと独自なものである場所を必死で探して行くだろう。
沖縄を愛する私たちにとって、沖縄のすべての場所、文化、習慣、歴史、言語が、たとえようもないほど大切なものなのだが、特にその社会の「共同性」は、私たちナイチャーにとって、もっとも憧れるものである。それはおそらく、私たちがまったく共同体というものから切り離されているからだ。日本のなかで孤立する私たちにとって、同じように日本のなかで孤立する沖縄の人びとが、あたたかい共同性のなかで暮らしているという事実は、これ以上ないほどのあこがれを呼び起こす。
このようにして、観光的で商業的な沖縄を心から軽蔑し、本当の沖縄、変わらない沖縄を求める人びとは、沖縄を「優しい場所」であると考えるようになる。あるいは、そうした「優しい場所」としての沖縄を、心から欲するようになる。どこかに、まだ観光地化されていない、商業化もされていない、なにも変わらない沖縄が残っていて、そこでは、人びとが、貧しいけれども豊かに平和に、優しい共同体のなかで暮らしているはずだと、私たちは思い込んでいる。
沖縄の社会構成の本質的な部分に、前近代的で非合理的な「共同性」があるということは、それ自体が「科学的に」検証されたことではないにせよ、経験的な事実としては、それは正しいように思える。たしかに沖縄の人びとは、模合などのさまざまな慣習を見るだけでも、私たち本土の都市部に暮らすものに比べれば、非常に強固で濃密な横のつながりのなかで暮らしているようにみえる(それが本土の地方部と比べてどのくらい「独自」であるのかは、また別の問題である)。
だが、沖縄の社会が経験してきたこと、沖縄のさまざまな場所に刻みつけられた記憶、沖縄の人びとによって積み重ねられてきたことは、決してそれだけではない。沖縄は共同性の島である。しかし、戦後の沖縄社会は、それだけでは語れない。
* * *
凄惨を極めた沖縄戦が終了したあと、沖縄の人びとは収容所に収容され、無人となった各地に強引に広大な基地が建設された。あるいは、ずっと前から暮らしている村を無理やり立ち退かされ、そこに基地が建設された。
収容所に収容された人びと、家や田畑を焼かれ奪われた人びとは、生まれた村を離れ、コザや金武などの基地周辺の街へ、あるいは、首座都市として急激に膨張しつつあった那覇へ移動した。1920年から1950年までの30年間、那覇市の人口は10万人前後で安定していたが、1950年から1975年の25年間で30万人にまで膨れ上がっている。沖縄戦とそれに続く基地建設によって土地を奪われた農民たちや、産業構造の変化のなかで農業に見切りをつけた人びとは、いっせいに都市に流れ込み、自由な労働力となっていった。
人口の激増と那覇都市圏への一極集中は、同時に、沖縄史においてまれにみる経済成長をもたらすことになった。戦後の初期の段階においては、米軍がもたらしたガリオア資金などの経済援助や公共投資などが、焼け野原だった沖縄に貨幣経済を復活させた。しかし、その後、沖縄経済は「自力で」発展していく。
その背景になったのが、この人口増加と都市化である。地方や離島から那覇に流れ込んだ人びとは、労働者でもあり、消費者でもあった。物価と賃金は連動して上昇しており、人びとは先を争って、アメリカや日本から輸入された消費財を購入し、貨幣を流動させた。この時期の沖縄は、公共投資よりも民間投資が経済成長を主導しており、貯蓄率も極端に低く、ある経済学者によって「分不相応な」と表現されたほどの消費ブームに沸いていた。都市に流入する人びとにむけて住宅需要が高まり、建設ラッシュが発生したが、またそのことが、更なる人手不足を生み出していた。いまでは信じられないことだが、ほぼ「完全雇用」に近いほどの低い失業率を達成していた。
50年代に経済成長が始まってから、わずか20年かそこらで、沖縄社会は根底から姿を変えた。60年代にはさらに離農が加速し、産業構造は第3次産業に偏っていった。
爆発的に拡大した都市は、その内部に、スラムや貧困、犯罪、暴力といった問題を抱えることになった。路上の突発的な暴力、共同体のなかの「血の鎖」のなかで発生する怨恨、ひたすら増殖する売春街、放置される不衛生なスラム、そして猟奇的な殺人事件。
このような社会状況のなか、特に人口を増加させていた浦添で、この事件は起きた。当時の浦添は、那覇のベッドタウンとして急速に拡大していた。戦前から1950年ごろにかけて、1万1000〜1万2000人で安定していた人口が、1960年には2万5000人まで急増している。10年で2倍以上になっているのだ。流入してきた人びとの多くは離島や北部などの周辺部出身者で、基地建設によって土地を奪われたり、農業を捨てて都市部で仕事を得ようとしていた。膨れ上がった那覇都市圏(那覇、浦添、豊見城、南風原など)のなかでも、浦添の人口の伸びはすさまじい。人口増加は高度成長期が終了してもとどまることなく、2000年には10万人を突破している。おそらく、沖縄の市町村のなかでは、もっとも人口増加が激しかったのが、この浦添である。浦添で生活史の聞き取り調査をすると、よく、「ここは寄留民の街です」という語りが聞かれる。寄留民とは、沖縄の表現で、「よそから移動してきて住み着いた人びと」のことだ。浦添は、戦後の人口増加と都市化によって拡大した、「移動の街」であった。
* * *
事件の主人公となったAは、地元の大地主だった親から、8000坪もの土地を相続で受け継いでいる。敗戦後に米軍が統治していた沖縄でも、日本の民法が有効とされていたが、それは戦前の明治民法で、たとえば事実上の長子相続である「家督相続」が認められていた。前代の戸主から次の世代の戸主へ、「家」のすべての財産が相続される制度である。日本本土では、戦後すぐに民法が改正され、この制度は廃止されたが、実はアメリカの施政権下におかれた沖縄では、かなり後までこの民法上の規定が残っていた。琉球政府によって古い民法上の規定が日本本土と合わせて改正されたのは、1957年である。私は、沖縄社会に色濃く残る「血縁規範」も、こうした戦後の歴史的条件がもたらしたものではないかと考えている。いずれにせよ、地主の長男であるAがすべての財産を相続できたのは、そういうわけだった。
そしてAは、せっかく譲り受けた家の財産を、すべて蕩尽してしまう。おそらく当時の浦添は、これから拡大していく那覇都市圏の重要な一部分として、いくらでも宅地の需要があったことだろう。Aのパーソナリティだけの問題ではなく、悪質な不動産業者などがいっせいに「地主のボンボン」であるAに群がっていたであろうことは、容易に想像できる。8000坪もの土地をすべて売り払っても、事件直前に手持ちの現金がほとんどなかったことから考えて、彼は、先祖から譲り受けた大切な土地を、二束三文で売り飛ばしてしまったのだろう。
被害者のB子は、宜野湾の真栄原の「飲食店」で働いていたが、Aに「身請けされた」というところから、この店はあきらかに売春宿である。沖縄の売春といえば、コザの照屋などの米兵相手の売春街がよく語られるが、言うまでもなく地元沖縄の男性相手の商売も、当時隆盛を極めていた。宜野湾の真栄原新町、あるいは「真栄原社交街」は、当時だけではなくつい最近になって沖縄県警が本腰を入れて排除するまで、非常に有名な売春街だった。多額の前借があったことから、おそらくは人身売買によって地方や離島から連れてこられて、住み込みで働いていたのだろう。当時はこのような、「貧しさからの売春」が多かった。こうした売春業や売春街の拡大も、戦後の沖縄史におけるひとつの重要な要素である。
また、B子の両親はブラジルに移民している。沖縄からの出移民は、戦後になってもおこなわれていたが、大規模におこなわれたのは戦前である。移民の全容についてはここで詳述できる余裕はないが、渡航費を自前で用意するケースも少なくなく、もしかしたらB子の「前借」とは、貧しい両親がブラジルで「一旗あげる」ための資金だったのかもしれない。
ブラジルへ移民したことと、B子が真栄原で働いていたことのあいだにどのような関係があるかは、いまとなっては一切不明だが、そこに「貧困」があることは間違いないだろう。そして、貧困の「解決法」が、戦前の移民から、戦後は本土出稼ぎと那覇都市圏への集中へと移行したということが、このB子の断片的な「家族史」のなかにも表れているのである。
そして、Aの、まるでストーカーのような異常な独占欲。定職にも就かず、犯罪を繰り返し、先祖から受け継いだ土地をすべて失ってしまったA。真栄原から身請けしたB子と所帯をもつときに、彼は自宅ではなく、わざわざ隣町で下宿を借りている。おそらく家族とは一切の縁が切れてしまったのだろう。彼は新聞記事のなかで、記者からのインタビューに答え、家族から見放されましたと答えているが、土地をすべて手放し真栄原新地の女性と結婚した彼は、事件の前からたったひとりきりになっていたのではないだろうか。甘い言葉ですり寄ってきた不動産業者やブローカー、あるいは犯罪者仲間たちは、このときにはすべて、彼のもとから去っていたことだろう。たったひとりになったAにとって、B子はどのような存在だったのだろうか。
そして、同じように、遠いブラジルの親から離れ、たったひとりで体を売っていたB子にとって、Aはどのような存在だったのだろうか。定職にも就かず手持ちの金も使い果たした彼のために、B子は小禄の空軍基地内でのペンキ塗りの仕事を見つけてきた。はじめのうちは二人で仲良く仕事にでかけていたが、やがてAはその仕事すら放棄してしまう。それでもB子は、Aのもとを離れようとはしなかった。事件当時、B子は妊娠4、5ヵ月だった。殺された夜、B子は、次の日の朝食のしたくをし、普段着で林のなかに出かけている。Aは取り調べのときに、「心中に失敗した」という主張を繰り返していたが、B子の様子からみて、Aを信じ切っていたようにみえる。その夜、真っ暗な雑木林のなかで、どのような会話がなされたのだろうか。
* * *
沖縄タイムスによって、「オッパイ殺人事件」と居心地が悪くなるほど「コミカル」な名前を付けられたこの事件だが、1959年2月27日、琉球民裁判所の下級審にあたる「巡回裁判所」で、懲役4年半の判決が下された。驚くほど軽いこの判決は、「承諾殺人」であるという被告の主張がかなり認められたことによる。当時は新聞記者による被告のインタビューが許されていたようだ。Aと記者との一問一答が掲載されている。彼はそのなかで、「判決は重すぎる」と語っている。
……上告しようと思う。……〔刑は〕重すぎる。これではまじめにもなれない(泣きべそをかいた表情)。……更正しようと思ってもこれではどうしようもないではないか。悪いことはしたが……近頃はいらいらする。[沖縄タイムス 1959.2.27]
Aが上訴したかどうかは明らかではない。これで刑期が確定したとしても、1964年ごろには出所しているはずだが、その後のAがどうなったのかは知る由もない。
* * *
この連載では、1960年前後の「沖縄タイムス」の記事から、戦後の沖縄の知られざる側面について述べようと思う。もちろん、わずか数年のあいだの新聞記事の、それもごく一部だけしか取り上げることができないので、これが戦後の沖縄の全てだと言うつもりはない。すべての記事を網羅しているわけでもないし、取り上げ方に一貫性があるわけでもない。ただ、たまたま目についた記事からでも、私たちは沖縄について多くを学ぶことができる。
次回以降、「共同体と暴力」「少年犯罪」「治安問題」「貧困とスラム」「売春と人身売買」などのテーマについて、断片的にだが、書いていきたいと思う。しばらくお付き合いくだされば幸いです。
(連載第2回以降はα-synodosで! → https://synodos.jp/a-synodos)
結婚ってなんだろう
渥美由喜インタビュー「なぜ『イケメン』ではなく『イクメン』がモテるのか――結婚とワークライフバランス」
齋藤直子「部落出身者と結婚差別」
牧村朝子インタビュー「自分の力だけでは、ままならないことがあった――フランスから同性婚を考える」
岸政彦「もうひとつの沖縄戦後史(1)──『オッパイ殺人事件』と経済成長」
山口智美「危惧される『婚学』のゆくえ———安倍政権下の男女共同参画との親和性」
サムネイル「at Taketomi, Okinawa on 11/Sep/1998」Motohiro Sunouchi
プロフィール

岸政彦
1967年生まれ。立命館大学大学院先端総合学術研究科教授。社会学。専門は沖縄、生活史、社会調査方法論。著書に『同化と他者化』、『断片的なるものの社会学』、『東京の生活史』、『図書室』、『リリアン』など。