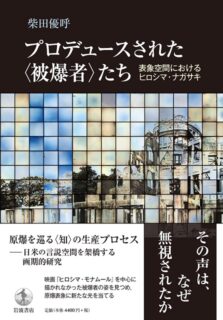2021.04.27
日米両国で、被爆者の怒りはどのように遠ざけられてきたか――『プロデュースされた〈被爆者〉たち—表象空間におけるヒロシマ・ナガサキ』(岩波書店)
『ヒロシマ・モナムール』は何の映画なのか
『ヒロシマ・モナムール』(アラン・レネ監督、マルグリット・デュラス脚本、1959年)というフランス語の映画と出会ったのは、アメリカの大学院で研究中のことだ。北米の人文学では、「ヒロシマと言えばこれ」というぐらい有名な映画だった。だが、どうしてこれがヒロシマの映画なのだろう? と疑問に思った。
被爆者は冒頭、説明もなくバラバラに挿入された映像の中に現れるだけで、彼らの声もその物語も出てこない。その代わり、広島を訪問中のフランス人女性を中心に、ストーリーは展開する。彼女は広島で一時的な関係をもった日本人男性を相手に、フランスでの自分の戦争体験を語る。ドイツ人の占領兵と恋に落ちたことで、裏切り者として地元の共同体から報復を受けたという過去についてだ。
この映画が示したのは、ヒロシマの「表象不可能性」である――と北米の人文学ではいわれている。ヒロシマが示唆する問題はあまりに大きすぎて、表象することができない、ということだ。被爆者の声を直接取り上げないのは、そうした「表象不可能」なヒロシマを、わかりやすい話に還元してしまうのを避けるため、とも説明されている。だが私にはピンとこなかった。それが本書の執筆につながった。
『ヒロシマ・モナムール』はヒロシマについての映画ではない、と私は考えている。脚本を書いたデュラスは、仏領インドシナで育った少女時代を題材に、自伝的小説『愛人(ラマン)』(1984年)を書いたベストセラー作家だ。この映画の奥底にあるのは原爆の暴力ではなく、植民地における「西洋の白人とアジアの現地人」の関係性についての、デュラスの記憶である。今でも『ヒロシマ・モナムール』は北米人文学の研究者のあいだで高い人気を誇っている。彼らがこの映画にこれほど魅せられるのは、デュラスが『愛人』同様、植民地主義の「魅力」を、異人種間の異性愛の寓話を通じてさりげなく描いているからなのだ。それは観客が被爆者の怒りや告発の声から目をそらすのを助けることになった。
被爆者の声が消されていった軌跡
一言でいうと、本書は、そのようにして被爆者の怒りや告発の声が遠ざけられ、じかに感じられなくされていった軌跡をたどったものだ。たとえば、『ヒロシマ・モナムール』はもともと、ホロコーストの犯罪性を告発したレネの『夜と霧』(1955年)に続き、広島の原爆を取り上げるドキュメンタリー映画となるはずだった。だがレネは途中でドキュメンタリーをつくることを断念する。そして、来日経験のないデュラスに脚本を依頼し、原爆被害を直接扱わない劇映画の制作に方向転換した。
『ヒロシマ・モナムール』に挿入された被爆者の映像についても、ほとんど目を向けられないできた。映像の提供元の一つは、日本映画社が米軍占領下、広島・長崎で撮影した記録映画で、1946年の完成と同時にアメリカに没収されたものだった。つまり、『ヒロシマ・モナムール』の公開時には存在しないはずの記録映画で、通称「幻の映画」と呼ばれたものだったのだ。こうした経緯から、この映像の使用は画期的なことでもあったが、先述のように、北米人文学の映画批評でとりたてて注目されることもない。人的被害の映像証拠を隠蔽しようとしたアメリカの行為は、素通りされたままだ。
レネがつくるはずだった映画の内容が変わったこと、敗戦直後に撮影された被爆者の映像が没収されたこと、その映像の使用が取沙汰されないこと——これらは積み重なって、被爆者たちの怒りや告発のもととなる証拠に、ベールをかけてゆくことになった。
日本でも一面的な被爆者像がつくられた
被爆者と観客のあいだを遠ざけるような措置は、日本でも行なわれた。『ヒロシマ・モナムール』は日本での封切時、ヒロシマのヒの字も出てこない『二十四時間の情事』という邦題に改題されたうえ、洋画専門館ではなく、ファン層の異なる邦画主体の映画館で公開された。その結果、観客動員は不振を極め、上映は早々に打ち切られた。当時国内では日米安保条約の反対運動が盛り上がっていたことから、「この映画を観客の目に触れさせたくなかったのでは」との疑いの声が後年、映画批評家のあいだで上がったほどだ。
もっとも、『ヒロシマ・モナムール』における被爆者の扱いは、被爆者に対する共感を引き出すようなものではなく、むしろその逆だった。当時最先端だったアヴァンギャルドの「洗練」された手法を通じ、レネは被爆者を、広島に新しく建設されたモダニズムの建築や意匠と並置し、その延長線上にあるような存在に変えている。
レネが出演交渉をした数少ない被爆者の一人だった吉川清も、そうした物言わぬ客体に変えられた。吉川は観光客らに積極的に自分のケロイドをさらすことで知られていた。それは原爆という巨大な暴力に対する怒りと告発を表す行為だったが、スクリーン上の吉川は、それとはかけ離れた存在にされていた。
『ヒロシマ・モナムール』では、亀井文夫のドキュメンタリー映画『生きていてよかった』(1956年)の映像も一部使用されている。亀井も、レネとは別のやり方で、のっぺりとした被爆者像を描きだした。それは被爆者を、原爆がもたらした悲劇を耐え忍ぶ「殉教者」のように捉えたものだった。実は亀井は制作当初、もっと多面的な被爆者像を織り込む予定にしていた。頭部にケロイドのある男子中学生が、原爆ドームに巣くう鳥を空気銃で撃って遊んでいる光景など、衝撃的な場面から映画をスタートするつもりだった。
だが、草創期の反核運動への配慮や、復興が進み「もはや戦後ではない」といわれるようになった時代の変化を反映し、結局「けなげな犠牲者像」と不協和音を生むような映像は、削除するに至った。それは被爆者の怒りや告発の気持ちを暗示させるような内容を、排除することにもつながった。
バッシングを受けた「わきまえない」女性作家たち
怒りや告発の声が直接抑えつけられるという経験をしたのは、自らの被爆体験を描いた女性の作家たちだった。『ヒロシマ・モナムール』の脚本を書いたデュラスが、北米人文学の「女性文学」(women’s literature)」という学問分野でスターのように扱われてきたのとは対照的に、原爆への怒りと告発を強く打ち出した大田洋子と林京子は、文壇からバッシングを受けた。
最近、東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の森喜朗・元会長の女性蔑視発言が批判を呼んだが、「わきまえない女」に対する風当たりの強さと、彼女たちの主張を忌避する動きは、原爆文学が世に出た当時から、連綿と続いてきた。その一方で、原民喜や井伏鱒二のように、抒情的にまたは「平常心」で語るとみなされた男性作家の作品は、教科書に採用されるなど、規範的な原爆文学としての扱いを受けている。大田も林も、彼らに比べると活動期間が長く、事実上原爆文学を牽引してきたのに、それに見合う評価は受けていない現状がある。
ただ、付け加えておくと、「わきまえない者」は大田や林だけではなかった。相手を問わずケロイドの傷を見せつけた吉川はもちろんその一人だったし、「幻の映画」を制作した日本映画社の関係者は、敗戦国であることを「わきまえず」、米軍占領下で原爆被害の記録を残そうとした。レネ自身、フランス政府の検閲と長く闘ってきた。『ヒロシマ・モナムール』にも、画面の外にあるアメリカの強大なプレゼンスに対する皮肉を暗示したように読み取れる要素を組み込んでいる。亀井も、戦争中は日本の中国侵略、戦後は軍国主義の批判が不徹底であることを批判した、まさに「わきまえない」監督だった。
ヒロシマ・ナガサキを巡る言説はこのように、様々なアクターによるせめぎあいと葛藤の歴史の中でつくられてきた。彼らは原爆という大きな物語に、単純に絡み取られたわけではなかった。本書では、そうした矛盾や複雑さを包摂することも心掛けた。
男性が支配する日本の学術・言論界
本書は、アメリカのコーネル大学に提出したPh. D. dissertationを書き直し、Producing Hiroshima and Nagasaki: Literature, Film, and Transnational Politicsとの題で、ハワイ大学出版社から2018年に出した単著をもとにしたものだ。今回日本で出版するのに当たり、大幅に加筆して再構成した。英語版は、これまで大学教員を務めたアメリカ、ニュージーランド、オーストラリアなどあちこちを移動しながらまとめたが、日本語版は日本で書き上げた。
興味深いのは、いる場所が変わるのにしたがい、知らないうちにその地における政治的・社会的ダイナミズムの影響を受けて、自分の中での力点も変化していったことだ。だから本書の中でも林や大田について書いた章は、私自身の実感を反映している。学術や言論の分野においても、圧倒的な男性支配がみられるのが今日の日本であり、長年海外で研究してきた身からすると、世界においても特異な姿となっている。それがまさに私たちが生きる日本の現実であり、その現実を見ないで書くことはできなかった。
プロフィール

柴田優呼
明治学院大学国際平和研究所研究員、アカデミック・ジャーナリスト。著書にProducing Hiroshima and Nagasaki: Literature, Film, and Transnational Politics (University of Hawaii Press、2018年)、『“ヒロシマ・ナガサキ” 被爆神話を解体する――隠蔽されてきた日米共犯関係の原点』(作品社、2015年) がある。このほか欧米で学術出版された英語書籍、朝日新聞取材班に参加して出版された日本語書籍など共著多数。アメリカ、ニュージーランド、オーストラリア、日本の大学教員を歴任。コーネル大学Ph. D.。