2015.12.02

日本のダイバーシティって、ぶっちゃけどうなんでしょう?
米国で10年にわたり経営学研究に携わってきた入山章栄氏の新刊『ビジネススクールでは学べない世界最先端の経営学』が上梓された。日本企業を取り巻くビジネス課題を、最先端の経営学の知見からやさしく解説し、話題を集めている。そもそも、日本のダイバーシティってどうなんですか? 「いい話」に隠されて本当のこと言いづらくなってない? みんなが聞きたい経営学アレコレに、経済学者・飯田泰之が迫った。(構成/山本菜々子)
最大の矛盾!?
飯田 新刊を拝読しました。なんてったって、章それぞれのタイトルがチャレンジグですよね。たとえば、「『チャラ男』と『根回しオヤジ』こそが最強のコンビである」とか「組織の学習力を高めるのは、『タバコ部屋』が欠かせない」だったり。
そもそも、本のタイトルである『ビジネススクールでは学べない世界最先端の経営学』がすごい(笑)。「ビジネススクールでは学べない」という本を早稲田のビジネススクールの准教授が書く……。
入山 最大の矛盾ですね(笑)。この本の告知をSNSでしたときに、うちのビジネススクールの学生から「先生、ぼくたちは学べないんですか」って連絡がきて。「早稲田の私のところなら学べるから!」と答えておきました(笑)。
飯田 本当にビジネススクールでは学べないかは置いといて、入山さんの本は、経営系、ビジネス書の中では特殊な本だと思っています。海外の最先端の知見を一般の人が手にとりやすい形で書いていて、実証分析を26ものテーマで紹介しています。
前著は、経営学のディシプリンを3つにわけて紹介するという方法論紹介色が強いものでしたが、今回は対象そのものが盛りだくさんな分、より「役に立つ」本なのかもしれません。
入山 ありがとうございます。社会科学は自然言語の壁がありますから、海外の最先端の知見はなかなか入って来づらいので、ぜひ紹介したかったんですよね。
それに、前回は理論から入りましたが、今回は、いまのビジネスマンの関心のある現象そのものから入っていきました。二年前に日本に帰って来て、日本のビジネスマンと交流していく中で、彼らのもっている問題意識を知ることができたんです。
たとえば、ダイバーシティひとつとってみても、海外の経営学では「デモグラフィー型」と「タスク型」という話が当たり前のように言われているのに、日本では全然知られていません。現在、ビジネスで直面している現象が、最先端の経営学でどのように説明されているのか紹介したかったんですね。
飯田 ぶっちゃけた話をすると、フレームワークを先に紹介して、実際の企業を挙げて書く方法って、ビジネス書として収まりがいいし読みやすいんです。たとえば、有名なマイケル・ポーターの「5 Forces」のフレームワークを紹介して、5章立てにして、それぞれに当てはまる日本の事例をもってきたら、けっこう綺麗にまとまった本が完成しますから。
一方で、入山さんはポーターの競争戦略論だけでなく、対抗するバーニーの「リソース・ベスト・ビュー」も取り扱う。複数の理論を併記するとどうしても教科書的になってしまいがちですが、ポーターvsバーニーを単純に対比させるのではなく、両戦略が適応される範囲の違いを「3つの競争の型」で解説しているところで「教科書化」を避けていますね。詳しいことは本で読んでもらうとして、背後にある議論、そのフレームワークの適用範囲まで一般書で踏み込んだ本は珍しい。
入山 一般にはあまり理解されていないのですが、経営学では、理論とフレームワークは別物です。「5 Forces」も理論ではなく、あくまでフレームワークです。本当はその背後に経済学の産業組織論の理論があります。そこまで勉強する時間はビジネスマンにないから、わからなくても噛み砕いて応用できるようにしたのが、たとえばマイケル・ポーターの「5 Forces」のフレームワークなんです。
私は米国のビジネススクールに10年いたのですが、率直に言って、ビジネススクールでは経済学の授業の人気があまりないんです。やっぱり、フレームワークやツールとしての「5 Forces」や、「人には何型人間がいて~」のような、あんまり深く考えずに学べちゃう方に行ってしまう。経済や組織のメカニズムって本当に理解しようとすると、しっかり学ばないといけませんからね。
飯田 経済の場合、なぜそれが役に立つのかわかるのに10年もかかったり。最悪の場合、実はそれには意味がなかったなんてことが発覚したりする……。
入山 (笑)。
そして、「メタ・アナリシス」
飯田 でも正直、ツール→事例っていうやり方だと、世の中何万社もあるんで、はまる事例は絶対でてくるんですよ。
入山 大事なポイントですね。ぼくも事例研究を悪いと思わない。むしろトップジャーナルの事例研究は素晴らしいと思っています。でも、ぶっちゃけ、ツールや理論に当てはまりそうな事例はどっかにある。それを拾って理論にあてはめれば、それっぽいことが言えてしまう。大きい声では言えませんが、ぼくも授業でたまにやっちゃいます(苦笑)。もちろん、この本にも理論→事例の順番で解説した部分もあります。
でも、社会科学なので、本当にそのツールや経営理論はどれくらい一般的に妥当なのかは、検証される必要があるはずです。そこで今回の本で重視したのは、経営学で最近重視されている「メタ・アナリシス」です。
簡単に説明すると、仮に、「M&Aをすると、企業の業績は低下する」という法則を実証分析した論文が100 本あったとします。そのうちの、60本はその法則を支持し、残りの40本は支持しなかったとき、私たちは「この法則は支持されている」と思っていいのでしょうか?
このような問題を解消するのが、メタ・アナリシスです。さっきの事例ですと、各論文で検出された主要な統計量(回帰分析の係数、相関係数、決定係数など)を膨大な論文から取り出します。そして、全体の総括として、「M&Aで業績は低下するのか」を検証します。

飯田 統計の統計というわけですね。
入山 そうです。やはり、同じテーマでも学者間で賛否両論あることはよくあります。メタ・アナリシスの結果を見れば、一本の論文をつかって自分の解釈に都合の良い結果を導き出すのではなく、今の時点での「ほぼほぼ学者のコンセンサス」に近いものを知ることができます。もちろん、そのメタ・アナリシスの結果も絶対だと思ってはいけませんが。
海外の経営学ではわりと一般的な手法で、最近はPhDの学生が博士論文の第一章で、先行文献のサーベイのような形でメタ・アナリシスを使うことが多いですね。
飯田 経営学に比べると経済学でメタ・アナリシスそのものをテーマにする論文は少ないように感じます。これは経済学、なかでもマクロ経済学の用いるデータの特徴によるものかなと思いますね。経営学では論文によって指数の作成方法など、データそのものが違うのが普通です。たとえば、本でも紹介されていた「産業効果と企業効果は何割ずつなのか」という問題では、各論文によって「産業効果」と「企業効果」の定義が違っている。だから、メタアナリスが有効なのかもしれません。
その点、マクロ経済ではマネーサプライやGDPだと定義がはっきりしているので、メタ・アナリシスというよりも。先行研究のレビューを並べることで議論の趨勢を把握できるという点はあるのかもしれません。
入山 実は、今回の本の中で一つだけ経済学のメタ・アナリシスを取り上げています。ブリティッシュ・コロンビア大学の著名経済学者キース・ヘッドの論文で、「グラヴィティ・モデル」と言って国と国の間の距離と貿易量の関係を分析した一連の研究のメタ・アナリシスです。近年は輸送コストの減少や情報技術が発展していますから、国どうしの距離が貿易量に与えるマイナス効果は弱くなっているはずです。ですが、実際にメタ・アナリシスで検証してみると、年々強くなっている可能性がある。
飯田 おそらくそれは、「距離」の定義が、直線距離なのか、時間の距離なのか、定義がばらけているので、それだとメタ・アナリシスをやる意味は大きいですよね。
入山 なるほどなるほど。加えて、経済学だと分析の手法がどんどん進んでいるので、20年前の回帰分析で出て来た結果は分析結果としてアウトオブデート(時代遅れ)だから、最近の新しい手法じゃないと信用できないのかも、とボクは思っています。
飯田 それはありますね。一番新しいものが正しいという感覚。これはぼくの直観なんで、なんのエビデンスもないのですが、経済学の古典的な手法では出なくて、新しい手法で出たものはだいたい信用できない気がする。
入山 ははは、なんとなくわかるかも(笑)。
飯田 古典的なものでやって、新しいものでやって消えた……というのは重要な研究なことが多いような。、その一方で、「新しい方法で新しい結果が出た」となると、それはデータや推計式をいじりすぎて偶然出ただけなんじゃないかと。もちろん、これは「気がする」だけなんで。あー、そう考えるとメタ・アナリシスは必要なのかもしれないですね。ぼくの直観がどのくらい正しいのかわかるかもしれません。
社会的に意義のあるものは、やる!
飯田 これまた個人的な関心なんですが、日本人は「いい話」が好き過ぎるんではないかと感じているんです。「いい話」については統計的な検証が甘くなる。なかには統計的に否定されていても「いい話」なんだから水を差すようなことを言うな!となってしまうことさえある。
たとえば、EM菌だって、「効果はほとんどない(むしろ、泥団子で汚染される可能性もある)」というのが科学者の大勢の意見なのに、「生徒みんなで環境のために一生懸命泥団子をつくっている、環境を考えることはいいことだ」でOKになってしまっている。
入山 本でも取り上げていますが、いわゆる「ダイバーシティ経営」もそういうところがありますね。これは、2013年の年末に日経ビジネスオンラインで書いたものを基にしたのですが、「『日本企業に女性はいらない』が、経営学者の総論」というタイトルをつけられて、かなり批判を受けました。
飯田 ……すごいタイトルですね。
入山 まぁ、タイトルはぼくの一存では決められないので(笑)。でも、内容としては、すごく真っ当なことを書いたつもりです。
経営学ではこれまでの研究の蓄積で、ダイバーシティには「タスク型」と「デモグラフィー型」の二種類があることがわかっています。タスク型は、実際の業務に必要な経験や能力の可能性です。その組織の人間がいかに多様なバックグラウンド、多様な職歴、多様な経験をもっているのかなどがそれにあたります。一方、デモグラフィー型は、性別、国籍、年齢など目に見える属性についての多様性です。
メタ・アナリシスの結果によると、タスク型はプラスの効果があるのですが、デモグラフィー型はプラスになるとは必ずしも言えない。むしろ組織にマイナスの可能性もありえることがわかっています。組織の中でデモグラフィーの違いがあると、「組織内グループ」ができ、男性対女性、日本人対外国人というグループ間の軋轢が生まれ、パフォーマンスが低くなってしまうのです。
そうなると、組織に重要なのは、デモグラフィー型の人材登用ではなく、タスク型であることがわかります。そもそも日本人の男性ばかりの組織に女性や外国人を無理矢理入れると、タスク型としてはプラスの可能性がありますが、デモグラフィー型としてはマイナスとなり相殺されてしまう。
だから、すごく乱暴な言い方をすると、「男性中心の日本企業に適したダイバーシティは、女性を入れずに、多用な職歴・教育歴の『男性』を採用すること」が、デモグラフィー型のデメリットを受けないため、経営学の理論的に正しいことになる。
でも、今のダイバーシティの受け取られ方って、今のままの環境で「とにかく女性や外国人を入れれば、すぐに業績がよくなる」という話にすり替わっている印象があります。「女性」「外国人」というデモグラフィー型のダイバーシティを目指しても、業績はアップすると限りません。
飯田 統計的な分析から考えると、「役に立つ」ダイバーシティのパターンはかなり明らかになりつつあるのに、いまだにダイバーシティなら何でもいっしょくたに論じていると。
ダイバーシティはロイヤルストレートフラッシュ級の「いい話」ですからね。「都合のいい話」と行ってもよいかもしれない。リベラル派はぜひ進めるべきだと主張し、現在は安倍政権の目標になっている。かつ産業界にとっても労働参加率を上げる必要があるから歓迎。だから、「みんなが支持しているいい話」だから「業績にもいいはずだ」という理屈のスーパージャンプがここで起きるんですよね。
入山 そうなんです。勘違いして欲しくないのは、ぼくは、女性や外国人を職場に入れるのは、社会的にはすごく意義があると思っていますし、どんどん登用されてほしい。
経営学の研究では、フォルトライン理論と言って、デモグラフィーがそもそも多次元に渡って多様であれば、組織内の軋轢が起きずスムーズになると言われています。
これまで「男性×日本人」だった職場に「女性×30代×日本人」を何人加えても軋轢になってしまう。でも、「女性×50代×日本人」や「男性×アジア人」「女性×40代×欧米人」が入ると一気に多様性の軸が増えるので、認知的に「男vs女」の軸の重要性が減って、組織内のコンフリクトが減ります。
いまの日本のダイバーシティはそこまで踏まえずに、男性中心の会社の中に、単に数値目標として一定割合の女性や外国人を登用しているだけの企業もあります。それなのに急に「ダイバーシティで企業の業績が上がる」という話になってしまったら、経営学者として「ちょっとまってよ」と言いたくなってしまう。
飯田 すごくよくわかります。オリンピックでもそうですよね。経済効果なんてほぼないのに、「経済効果」ってすぐ言うじゃないですか。
入山 えー!オリンピック、そうなんですか。
飯田 ジェフリー・オーウェン(インディアナ州立大学教授)のサーベイ論文では、多くのメガイベントに経済効果はないというのがこれまでの研究の大勢であることが示されています。イベント中の外客の増加は、イベントがなかったら来ていたであろう人をクラウド・アウトするだけです。そして土木建設工事の方に経済効果があるとしたら、それはメガイベント関係なしに公共事業を増やせばいいというだけの話ですから。
とはいえ、ぼく自身は、東京オリンピックはすごく応援しているんですよ。だって、お祭りだし、東京でやるのが単に楽しみです。でも、「経済効果はない」と経済学者だから言うと、「水差すな」ってけっこう怒られたりするんです。
ダイバーシティの話も同じだと思います。企業の業績とはあんまり関係ないかもしれない。だけど必要なんですよ。オリンピックも、経済効果ないかもしれないけど、「やりたいからやろうよ」でいいじゃないかと。
入山 それだと話が通りづらいんでしょうね。数字的な根拠が必要なので、どこかの調査会社に怪しい経済効果の計算をしてもらう(笑)。
飯田 そういうときに、「いや、経済効果がない」と言うと、冷たい人みたいになってしまいますしね。冷静な現状分析とこうあって欲しいことは結びつかないことがある。べき論と統計的な特性は違うんだと。
入山 ぼくも「アメリカの経営学者はドラッカーを読んでない」と言ったら「入山はドラッカー読むべきでないと言っている」と勘違いされたことがあります。
飯田 そういう話じゃないですよね。アメリカの経営学者や院生が読んでいないからこそドラッカーを読め……という主張もありえるわけですから。繰り返しますが、「経営学的」に「経済学的」にマイナスの効果だったとしても、社会的に意義のあるものはやる! ぼくはそう思います。
学問のダイバーシティ
入山 ちなみに、聞きたかったんですけど、飯田さんはピケティについてどう思っているんですか。
飯田 これはまさに今お話したダイバーシティと関わってくると思います。彼は、ハーバードでトップレベルの数理的な研究もやっていたんですが、いまはフランスで歴史的なデータを中心とした研究、難しい数理や統計技法不要の研究研究をしている。
これがフランスの懐の深さかなと思うんです。アングロサクソンスタイルの、いうなればノーベル賞向きの研究を行う研究機関と、数理的なモデルや統計分析をつかわないフランス独自の経済学をする研究者を雇う大学がある。そして、後者の方から、一世代に一人ピケティのようなスーパースターが出てくる。
入山 なるほど。もしかしたら、日本の経営学もそういうところがあるのかもしれません。ぼくは、「日本の経営学は国際化されていない」とよく言うので、なぜか日本の経営学の事例研究を批判していると思われがちなんだけど、実はみなさんかなり面白いことをやっているなあ、と思っているんです。
飯田 そうそう。だから、全部をアメリカらしい徹底的なジャーナル主義にする必要はないと思うんです。「超ガラパゴスな研究を続けて、30年後にすごい発見があった」みたいな出世方法があってもいい。両パターンの研究者が併存することで、日本国内の学者の中でスキルのダイバーシティが起こるんじゃないかな。
入山 経済学は良くも悪くも国際標準に染まり過ぎているのですかね……
飯田 変わった分析をする人がなかなか出てこないのはもったいない。やっぱりピケティが登場したのはフランスの学会のダイバーシティのおかげだと思います。
入山 一方でそこでは国際的なレベルでの競争に晒されないから、すごいモラルハザードがおきるのかもしれません。だからせいぜい一世代に一人なんでしょうね。
飯田 ですね。当たり外れも大きいし、サボろうと思えばいくらでもさぼれちゃう。その一方で、経済学者からすると、事例研究中心の経営学はどうも厳密さ欠ける気がするのは確かです。そのためか、どうしても「経営学はビジネス書を難しくしたものでしょ?」みたいに感じてしまいます。
入山 でも、世界のトップジャーナルに載る経営学の事例研究って、実はハンパないんですよ。一本の事例研究書くのに、平気で200人くらいにインタビューしたりするんです。
飯田 へぇー、事例研究というより調査になっている。
入山 本当のトップジャーナルの事例研究は会社の中に深く深く入り込んで、すごい場合は10年近い時間をかけて、トップから末端まで何十人、何百人にインタビューして、内部の会議にもいくつも出席して……と本当にすごいんです。
飯田 それはすごいなぁ。普通、できないですよね。
入山 ですから、もしみなさんが経営学の事例研究を「会社の数人にインタビューして、関連本を読めば事例研究」と思っているのであれば、それは世界標準の事例研究とは全然違いますね。ボクは統計分析をつかった研究を主にやりますが、正直海外トップジャーナルを狙うレベルの事例研究をやるのは嫌ですね(笑)。たいへんすぎる。
たとえば、「イノベーションのジレンマ」で有名なクリステンセンが、著者の一人となって最近「ストラテジック・アントレシップ・ジャーナル」に発表した「イノベーティブな起業家」についての論文があります。
これまでの経営学では、「起業家」といっても範囲が広範だったんです。極端に言えば、スティーブ・ジョブズのような人から、細々とラーメン店を開業した人までをすべて「起業家」と言っていたわけです。だけど、クリステンセンは「これまで存在しなかった製品・サービスを生み出し、世界にインパクトを与えた起業家」22人にしぼり、その思考法などの研究を行ったんです。
その調査対象がまたすごく豪華なんですよ。ジェフ・ベゾス(amazon)、マイケル・デル(デル・コンピューター)、ハーブ・ケラー(サウスウエスト航空)、ニクラス・ゼンストローム(スカイプ)……まさに超著名な起業家ばかりです。
これは、クリステンセンの高い知名度があったからこそできた研究だと思います。これはひとつの極端な例ですが、このように世界の経営学の事例研究は本当にすごいところまで来ていると思います。ちなみに、この研究から得られた知見は、私の新刊に書いてあるので、ぜひ読んでみてください。
飯田 クリステンセンだから可能な研究かもしれない(笑)。ですが、やはりどっちが良い悪いじゃなく、スキルのダイバーシティが必要だということですね。

ビジネスマン必見!
飯田 最後に、この本はどんな方に読んで欲しいですか。
入山 ぼくの本は、もちろん学生さんにも読んでもらいたいのですが、特に社会人の人にはぜひ読んで欲しいと思っています。というのも、早稲田大学ビジネススクールのボクのゼミには、ビジネスマンの学生が何人もいます。多くは20代後半〜40代前半の、現役でバリバリ働いている人たちです。なので、彼らと世界のトップジャーナルの論文を読んで議論すると、学生とはいえすごく面白い議論ができるんです。
飯田 自分自身がビジネスの現場にいるからでしょうね。事例ってエビデンスにはなりがたいですが、理論を飲み込むための導入剤やオブラートになる。現場にいる人は身をもって事例を知っているから、理論を飲み込みやすいんでしょう。
入山 まさにそうなんです。本でもふれましたが、最先端の組織学習研究で研究されている「トランザクティブメモリー」というものがあります。組織の記憶力のことです。
社内間で情報共有が必要なことは明らかですが、その時に全員が全員の情報を知っている必要はありません。組織の「誰がなんの情報をもっているのか」を知っていればいい、というのがトランザクティブメモリーの考え方です。
最近経営学のトップ学術誌である『アカデミー・オブ・マネジメント・ジャーナル』に発表された出新しい学術論文で、組織の全員がそのようなトランザクティブメモリーをもった方がいいのか、それとも組織には「トランザクテイィブメモリー屋」のような人がいて、その人に集約させた方がいいのか、という疑問を実験したものがありました。その結果、後者の方が組織にはいいという結果になったんですね。
飯田 なるほど。ハブがいたほうがいい。
入山 3人に均等にトランザクティブメモリーを与えた場合と、一人だけに集約されて他の人は知らないというグループで共同作業をさせると、明らかに後者の方が能率がいい。
飯田 つまり、「トランザクティブメモリー屋が誰か」を知っていればいいわけですね。
入山 そうです。そこで面白かったのが、その論文が説明する理論メカニズムによると、「トランザクティブメモリーを特定の人に集約させると、その人のふるまいが心理的に変わって、他の人の情報を提供するような行動をとるようになる」という因果関係の説明だったんです。
でも、ボクのゼミ生は自分たちの仕事の経験から、「絶対に因果関係が逆です」といいはじめて。「そういうトランザクティブメモリーの情報があったからって、急にギブアンドテイクするようになるのは、ぼくたちの現場では考えられない。むしろ、そもそもそういう性質をもった人が、トランザクティブメモリー屋になるんだ」と。
彼らは、色んな経験をしているので、とても最先端の経営学の実験でやっている考え方について、現実はそうではないと議論することができるんですね。でもそれは、理論という軸と、実験による厳密な分析結果がベースにあるからできることです。
こういったことができるのが、世界先端の経営学を学ぶ魅力のひとつであり、そしてそれを日本のビジネス課題に引きつけて書いている唯一の本が、私の新刊です。だからこそビジネスマンの人にこの本を読んでもらって、最新の知見に触れてほしいと考えています。
プロフィール

飯田泰之
1975年東京生まれ。エコノミスト、明治大学准教授。東京大学経済学部卒業、同大学院経済学研究科博士課程単位取得退学。著書は『経済は損得で理解しろ!』(エンターブレイン)、『ゼミナール 経済政策入門』(共著、日本経済新聞社)、『歴史が教えるマネーの理論』(ダイヤモンド社)、『ダメな議論』(ちくま新書)、『ゼロから学ぶ経済政策』(角川Oneテーマ21)、『脱貧困の経済学』(共著、ちくま文庫)など多数。
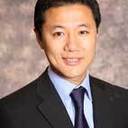
入山章栄
慶應義塾大学経済学部卒業。同大学大学院経済学研究科修士課程修了。三菱総合研究所で主に自動車メーカーや国内外政府機関への調査・コンサルティング業務に従事した後渡米し、2008年に米ピッツバーグ大学経営大学院より博士号(Ph.D.)を取得。同年より米ニューヨーク州立大学バッファロー校ビジネススクールのアシスタント・プロフェッサー(助教授)に就任。2013年に帰国し、早稲田大学ビジネススクール准教授し現在に至る。専門は経営戦略論および国際経営論。Strategic Management Journal、Journal of International Business Studiesなどの国際的な主要学術誌に論文を発表している。おもな著書に『世界の経営学者はいま何を考えているのか』(英治出版)。


