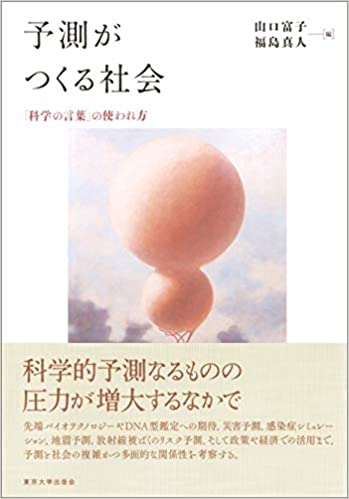2020.08.03

自己破壊する予言――感染症数理モデルの行方
分裂する世界
サイエンスフィクションをはじめ、物語の世界では、ある一時点の選択をきっかけに異なるストーリーが展開していく様がときどき描かれる。たとえば映画『スライディングドアー』では、主人公が発車間際の地下鉄列車に乗り込めた世界と、そうでなかった世界の両方が並行して描かれていく。乗車という選択の時点で世界はいわば2つの世界に枝分かれし、両者はクロスすることなく異なる結果に向かう。ほかのSFでは分裂した2つの世界を横断する旅行者が登場してやんやと話を盛り上げる場合もある。とはいえ多くの物語は、枝分かれしたもう片方の世界を私たちがけして見ることができない点をほのめかすものだ。この「分裂する世界」をヒントにこのたびの感染症問題を考えてみたい。
このたびの新型コロナウイルス感染症は世界中に大きな混乱を招いており、これにどのように対処すべきかの議論が紛糾している。2020年原稿執筆時点(2020年6月)の日本では緊急事態宣言も解除され、落ち着きがみられるようになってきた。そうした中、日本で講じられてきた対策はむしろ過剰だったのではないかという批判も生じつつある。一連の論争で焦点があたっているのが、厚生労働省に設置された専門家会議と、そのメンバーである北海道大学の西浦博教授(数理疫学)が示した新型コロナ感染者数の試算である。「人と人との接触を減らすなどの対策を全く取らない場合、国内では重篤患者が約85万人」という試算は衝撃的であったようで、「42万人死亡」、「8割おじさん(接触の8割削減を強調する西浦教授を指して)」などの文言がニュースで踊った。当時からその内容には批判も向けられていた。
批判の内容には、「過剰防衛を行うことへの批判」と、「数理モデルを活用した試算への疑念」の二つが微妙に重なり合っている。しかし、こうした批判はより根本的な問いを提起するものでもある。すなわち、「未来への予測をもとにした政策と、その結果との間の関係を、私たちは正確に理解することができるのか」という問いである。
英雄から幻想へ――イギリス口蹄疫での数理モデル
ここで現代からすこし過去にさかのぼってみたい。人々は見えない敵である感染症に対して、病気に感染した人の隔離、ワクチンの開発などさまざまな対策を講じてきた。感染症対策の長い歴史の中で、対策の武器の一つに数理モデルが加わったのは比較的最近のことである。イギリス政府が2001年の口蹄疫(家畜の間で伝染する病気)の対応に数理モデルを活用したのが最初のケースといわれている。口蹄疫が発生した当初、イギリスの対策本部は家畜へのワクチンの接種や自然治癒を待つゆるやかな対応をとっていた。しかし、1か月後にはコントロールが不可能になってしまい、家畜の処分にかかわる意思決定の際に数理モデルの専門家チームの提言を参照している。感染症にかかわる過去のデータを扱うモデル研究はそれまでにもあったが、このイギリスの例は感染症の発生が起こったまさにその最中にモデルを参照したという点で先駆的だったといえる。
専門家チームは数理モデルの試算を通じて、感染症が発生した農場の周囲3キロメートル以内の家畜の全殺処分が有効だとする主張を行った。これを受け、対策本部は家畜の処分という強硬な対策へと移行する。しかしこの対策には後に批判も向けられており、数理モデルの誤用によって健康な動物も多く処分された、被害をむしろ拡大させたとする意見も出ている。感染症への対応をどの程度厳しく設定すべきかのさじ加減は誰にもわからない。その中で数理モデルを参照して比較的ハードな対応策がとられ、後に批判される構図は今回の日本のコロナ感染症とも共通している。
数理モデルという存在が突出的に目立ってしまいバッシングを受ける現象――とくにメディアの中で――もこのイギリスの口蹄疫パンデミックですでに生じている。ネルリッヒ(科学社会学・メディア論)は、当時のイギリス新聞メディアに登場した「数理モデルのメタファー」を調べており、数理モデルと研究者が英雄視された後に、批判の矢面に立たされた様子を明らかにしている。イギリス新聞メディアは数理モデルに対してはじめのうちは好意的であり、研究者を「追跡ツールを駆使する探偵」や「強力な武器をもった英雄」と賞賛していた。ほかにも「水晶玉を扱う魔法使い」など、初期には、数理モデルをポジティブに報道する記事が目立つ。
他方、興味深いことに、記事の中には、数理モデルがあたかも病気そのものと同じであるかのように表現するものが登場し始める。数理モデルを擬人化するメタファーも出てくる。家畜の全殺処分という対策本部の方針が決まった後はさらに風向きが変わり、モデルに批判的な記事が増える。そうした記事で用いられる数理モデルに使われるメタファーは、「時代遅れの武器」、「幻想」「虚偽」であった。ネルリッヒは、こうした批判的なメタファーの発信者が、実のところ口蹄疫問題の決定プロセスから除外されたと感じる(他領域の)専門家だったことも明らかにしている。
予測の不思議なふるまい
モデルはどうやらその後の対策がうまくいってもいかなくても叩かれやすいという難題を抱えているようだ。モデルにもとづいた対策がうまくいき、感染が抑えられたとしたら、それまでに講じられた対策――口蹄疫の場合は全殺処分であったり、今回の新型コロナ問題では接触機会の低減であったり――は、不要だったのではないかと批判される。しかしながら、感染が抑え込めず重篤患者数や死亡者数が膨らんだときには、それはそれでモデルおよび対策に批判が集まることは想像に難くない。感染症の拡大予測は、社会が感染症を抑えることに成功すると結果として外れる。ただしこのとき防止のため諸々のコストが費やされるので、予測の前提や用いるデータが間違っていたのではないかという批判が常に後から生じる。
予言がなされることで、もしそれがなければたどったであろうシナリオから外れさせ、結果として最初の予言が間違っていたことになる現象を「予言の自己破壊的性質」という。これは、予言の自己成就(未来についての予言に対して、人々がその予言を信じて行動することによって、結果として予言通りの現実がつくられる現象)で有名なマートンが唱えた概念である。災害の防止や、組織事故の防止の中にも予言の自己破壊はみられる。たとえば、地域住民に対する「津波が来ますよ(このままだと死んでしまいますよ)」という警告はある意味で未来への予言である(山口富子・福島真人編『予測がつくる社会』では、地震予測、経済予測、防災、新技術への期待など、社会のさまざまな領域にある未来への語りの振る舞いを扱っている。筆者は「感染症シミュレーションにみるモデルの生態学」(第5章)にて感染症問題を論じている)。しかしこれを信じることが、未来のシナリオを変更する行動――避難行動のような行動へと導く。うまくいく防災とは予言の自己破壊的な性質をうまく活用できたものだといえよう。
また一般の組織にも予言の自己破壊はある。最悪の状態を想定し、その防止策をとることで、最悪の状態は回避される活動が常日頃より行われている。安全という状態は常に何かしらの防御策が動いていることによって成り立つのである。福島が『学習の生態学』で詳しく論ずるように、問題は、防御がうまくいくときにはその防御がみえにくい点にある。そのため結果として見えている安全に対して、そこにかけているコストが多すぎるという批判が常に生じてしまうのである。感染症をめぐる問題も、こうした一般の組織で安全を保つときのジレンマと同じ構造を持つといえる。
このほかにもさまざまな領域(地震や経済等)で予測の不思議なふるまいが見られる。予言の自己成就が起こりやすいトピックもあれば、今回の感染症問題のように予言の自己破壊の理解が重要となるトピックもある。いずれにせよ、予測は、「未来は何々となる」という記述が、必ず「何々を目指すべし/何々を避けるべし」という行為に向けてのメッセージをともなうことで社会と複雑な関係性を結ぶのである。
もう片方の世界?
「未来への予測をもとにした政策と、その結果との間の関係を、私たちは正確に理解することができるのか」という問いに立ち戻ると、予測というものの性質上、できない、というのがここでの答えになる。そもそもある政策の介入(原因)とその効果(結果)の因果関係を厳密に検証するのは難しい。政策以外の条件がまったく同じである複数の社会を用意し、対比的な実験を行うのが難しいためである(実験の手法では、一つの群(グループ)に特定の条件(X1)を加え、そこで生じる結果(Y1)を見るだけでは不十分である。条件を加えなかった群(コントロール群)(X2)で生じる結果(Y2)と照らし合わせることではじめて、条件(X)が結果(Y)の原因であるとされる。このとき、厳密には、実験で設定する条件以外の諸々の条件はすべて同じである必要がある)。もちろん多くの国・地域のデータを集めることで、ある程度の連関を示すことはできる。実際そうした横断的な検証も始まりつつあるようだ。しかしそうした連関のデータが示されるまでは、対策は過剰だったのか、あるいは、適切だったのかを評価することはできない。
さらに本質的な問題として、私たちはやはり一つの世界しか見ることができないという宿命をかかえている。ふたたび、映画『スライディングドアー』を取り上げれば、物語を眺める観客は、二つに分裂した世界を――主人公と恋人との異なる顛末などを――比較しながら眺めることができる。しかし私たちにとってはいくら選択が続こうとも実世界は1つである。分岐した世界はあくまで実世界からの仮想にすぎない。未来への予測と、それをもとにした行動が複雑に絡み合って作られた帰結が唯一の実世界なのだ。
ここでは最後に、激しい批判が、数理モデルやその研究者個人に集中することは何故なのかも問うてみたい。この点あらためてネルリッヒの指摘は興味深い。彼女の新聞分析では、感染症の数理モデルが「感染症そのもの」であるかのように扱われていった様子を明らかにしていた。モデルは現実の現象を模したものであるからして、現象(今回の場合は感染症そのもの)とは異なる。しかし、モデルはその現象を表現しているため、意味的なつながりは保持されている。数理モデルは、モデルが災厄そのものを引き連れてきたようにみえてしまう宿命を背負っているのかもしれない。
私たちの社会は、こうした特性をもつ数理モデルの扱いを学びながら先に進んでいくのだろう。実は筆者は、コロナの問題が生じる前に感染症の数理モデルがどのように政策に活用されているのかの社会的研究を行ってきた。日本と台湾の専門家にヒアリング調査を行い、数理モデルの受容にかかわるさまざまな社会的要因を考察している(『予測がつくる社会』)。また別稿(日比野「感染症数理モデルの棲まう場所――日本と台湾の比較から」『UP』(東京大学出版会)近刊)では日本と台湾との相違点を検討している。関心のある方にはご一読いただければ幸いである。
とあるSFでは、主人公が分岐した別の世界の存在を知りそちらに移動しようとしたところ(文字通り)身体が引き裂かれて死んでしまう、えらく物騒な結末を迎える。もう一つの世界への幻想に私たちは十分に注意する必要がある。
プロフィール

日比野愛子
弘前大学人文社会科学部教授、博士(人間・環境学)。モノ(テクノロジー)と人間集団との相互作用に着目し、合成生物学(培養肉)をはじめ、感染症シミュレーション、アグリ・イノベーションなどのトピックや、ゲーミング・シミュレーションの研究を行っている(研究室ウェブサイトhttp://www.fibonacci-ah.net/)。著書に、山口富子・日比野愛子編著『萌芽する科学技術――先端科学技術への社会学的アプローチ』(京都大学学術出版会,2009年)、山口富子・福島真人編『予測がつくる社会――「科学の言葉」の使われ方』(分担執筆、東京大学出版会、2019年)、日比野愛子・鈴木舞・福島真人編『科学技術社会学(STS):テクノサイエンス時代を航行するために』(新曜社,2021年)ほか。